<不正義の平和よりも希望の戦争を>
2月24日。朝から強い凍った北風が、新宿の摩天楼を突風の様に突き抜けていた。私はダウンの襟を立て、ポケットに手を入れ少し前かがみになりながら、靖国通りと青梅街道の起点、新宿大ガードをくぐった。ガード下の、湿って冷たく凍りついた布団にくるまっているホームレス達を横目で見ながら、「この人達も希望は戦争なのかな?」と、思わず一人一人に聞いてみたくなった。途中、知っているホームレスの親分から(彼らが街頭販売をしている雑誌)『THE BIG ISSUE』を1冊買いながら、「どう? この冬は?」と聞いてみた。「今週は4人死んだ。兄さんの景気はどうだい?」とその親分はぽつりと言った。私は、その声を背に歌舞伎町セントラル通りに入り、ロフトプラスワンに向かう。目的は、かの赤木君に会うことだった。
この日のイベント紹介文にはこう書かれてあった。
『論座』誌上で「希望は戦争」と宣言して巨大な反響を巻き起こした赤木智弘と、「正義の戦争」を唱え続けるファシスト佐藤悟志が、不正と格差に満ちた現在の平和を罵り倒し、市民運動業界の禁句「戦争」を正当化する!
【司会】佐藤悟志(『青狼会』総統/『売春の自由党』事務局長)
【Guest】赤木智弘(『若者を見殺しにする国』著者)
ここで世の文化人を驚愕させた『論座』4月号(朝日新聞社)の赤木論文の抜粋を、知らない人たちのため紹介しておこう(丸山眞男ぐらいは検索をかけておいてくれ)。
「『丸山』をひっぱたきたい 31歳フリーター。希望は、戦争。」(抜粋)
●私は親元に寄生して、自分一人の身ですら養えない状況を、かれこれ十数年も余儀なくされている。31歳の私にとって、自分がフリーターであるという現状は、耐えがたい屈辱である。月給は10万円強。北関東の実家で暮らしているので生活はなんとかなる。だが、本当は実家などで暮らしたくない。できるなら東京の安いアパートでも借りて一人暮らしをしたい。しかし、今の経済状況ではかなわない。
●平和な社会を目指すという、一見きわめて穏当で良識的なスローガンは、その実、社会の歪みをポストバブル世代に押しつけ、経済成長世代にのみ都合のいい社会の達成を目指しているように思えてならない。このようなどうしようもない不平等感が鬱積した結果、ポストバブル世代の弱者、若者たちが向かう先のひとつが、「右傾化」であると見ている。(右傾化する若者が)不満や被害者意識を持っているというなら、なぜ左傾勢力は彼らに手を差し伸べないのか。
●私のような経済弱者は、窮状から脱し、社会的な地位を得て、家族を養い、一人前の人間として尊厳を得られる可能性のある社会をもとめているのだ。そのために、戦争という手段を用いなければならないのは、非常に残念なことではあるが、そうした手段を望まなければならないほどに、社会の格差は大きく、かつ揺るぎないものになっているのだ。反戦平和というスローガンこそが、我々を一生貧困の中に押しとどめる「持つ者」の傲慢に対して、一方的にイジメ抜かれる私たちにとっての戦争とは、現状をひっくり返して、「丸山真男」の横っ面をひっぱたける立場にたてるかもしれないという、まさに希望の光なのだ。しかし、それでもやはり、我々を見下す連中であっても、彼らが戦争に苦しむさまを見たくはない。だからこうして訴えている。私を戦争に向かわせないでほしいと。
 |
ロフトプラスワンでの赤木君と佐藤氏のトーク。佐藤氏の「戦争論」の過激さに、かの赤木君はちょっととまどい気味だ。
「僕はファシストじゃない」って言いたげだった。でも内容のある議論だった。君も来れば良かったのに |
この赤木論文は、どこか私には説得力があった。だからどうしても彼と会いたくなったというわけだ。
日曜日の午後2時、私が会場に入ったときにはイベントはもう始まっていた。場内は何か異様に暗かった。雨宮処凛の「プレカリアートに力を!」みたいな力強さはなかった。私は、赤木君と直接話すのは初めてだ。壇上にいる純朴そうな青年は、暗く苦渋に満ちた顔色をしていた。今の格差社会の底辺にいる「明日に希望のなくなった若者達」の暗い部分を見た感じになった。後半、私は直接マイクを持って反論を開始した。真摯に私の質問に受け答えしてくれる赤木君に、私はとても親しみを持った。多分、赤木君は自分の目の前にある「現実」に直面し、どうしてもイメージできない将来を悲観しているのだと思った。ふっと私は、佐藤氏と赤木君のトークを聞いていて、「希望のない青春」を経験したことがない自分に気がついた。ここで私は赤木君に論争を挑むことの愚かさを知った(詳しくは本誌の佐藤悟志レポートを読んでくれ)。
<おじさん流 阿佐ヶ谷ロフト奮戦記−3>
阿佐ヶ谷ロフトが新規開店し3カ月が過ぎた。毎日毎日、それは興奮した一日が過ぎ去ってゆく。3月に入って、阿佐ヶ谷ロフトのライブの客入りが、3人を最低記録に、20人以下の客入りが3〜4日続いた。私は、このままでは潰れ得るという危機感を感じた。阿佐ヶ谷ロフトのライブの柱は「地球環境・社会・政治問題・市民運動・地域密着型」にしようと思っていたし、これらのコア企画のほとんどは私が立案した。しかし、現実は厳しく、これらのテーマの日の動員は芳しくない。
 |
今月の阿佐ヶ谷ロフトの美女軍団は2人も紹介するぞ。知り合いになりたい奴は店に飲みに来い。名前はべべちゃん(左)とるーちゃん(右)。もうすぐお花見もやるからチャンスだ。次回から女性愛読者のために阿佐ヶ谷ロフトが誇るイケメン軍団を紹介するぞ(笑) |
イベントの宣伝は、本誌『Rooftop』(発行5万5000部)、月刊誌『創』巻頭1p広告。それに阿佐ヶ谷ロフト独自のチラシを、2万枚は店や各方面に撒き、5000枚は、阿佐ヶ谷近辺の朝日・読売・日経の新聞へ折り込んでもいる。もちろんHPを始めネットでも告知している。それでも20人ぐらいしか入らないイベントが沢山ある。入場料1000円だとすると、お客20人だと2万円の売り上げだ。「すみません、申し訳ないけど、今日のギャラは交通費程度で我慢してください。その代わり飲ませます」と、その日のゲストに告げなければならない時は本当につらい。しかし、これが阿佐ヶ谷ロフトの現実なのだ。
と思っていたら、昨夜の阿佐ヶ谷ロフトは満員。「おにいちゃんCD発売記念」だと。お客さんもよく飲み食いしてくれる。あどけない少女の煽りに乗ったアキバ系オタクのオヤジどもが興奮していた。いいな……(苦笑)。
 |
春の和田堀公園の梅林を歩く平野さん |
今月も、道路拡張問題や駅前開発問題を地元住民の側から考える「<都市会議>4つの町をつなぐナイト。」(4/2)とか、圏央道開通による自然破壊問題がテーマの「『高尾山に穴があく!?』〜高尾山圏央道建設計画について考えよう〜」(4/3)なんて企画があるが、はたしてイベントとして成立するのか?「平野さんはどこもができない、成立しないと思われるイベントを商業ベースでやろうとしている。凄い」とはよく言われる。確かに市民運動系のイベントはみんなボランティアペースで、街の小さな公営ホール(会場費はほとんど無料)でひっそりとやられたりするのだが、はたして私の「社会の現実と向き合った企画」がいつまで続けられるのだろうか、ちょっと心配になってきた。エンタメオンリーでいくしかないかとも思うが、それでは何のために阿佐ヶ谷にロフトを作ったのか分からなくなるのが怖い……。
いつからともなく春が来て、梅の花が満開になってきた。私は、ズボン下を脱いで、自転車通勤を始めた。季節の移り変わりに年寄りは敏感だ。桜上水から荒玉水道を抜け、善福寺川沿いを通って阿佐ヶ谷に向かう。今年初めてのモンシロチョウと出会った。蚊柱にも会えた。大宮八幡からの善福寺緑道は、もうしっかり春の訪れを予告していた。新緑の空気が素晴らしい。桜庭一樹の138回直木賞受賞後第一作「冬の牡丹」(『オール讀物』3月号収録)はいい。これぞ文学っていう感じかな?
今月の米子
陽だまりの米子。時折、私が春の陽光の中で新聞を広げていると、じゃまをしに来る。これでは新聞が読めない。
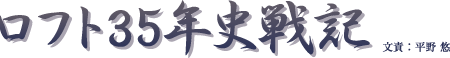
ロフト35年史戦記・後編 第36回 新宿ロフトプラスワン編−4(1995年〜)
「こうして歴史的伝説は作られた。」
<「チャージはいらねぇ〜」1000円でおつりがくる店を目指した>
1995年7月6日、ARBのドラマー・キースを一日店長(当初プラスワンでは当日のメイン出演者を一日店長と呼んでいた)に迎え、ロフトプラスワンはオープンした。世界初のトークライブハウス「ロフトプラスワン」は、現在までの13年間で、のべ6000人以上の「一日店長」と、その数十倍のゲストを迎えてきた。それはもう壮大な歴史である。
当初のプラスワンのイメージは、明らかに既存の音楽系ライブハウスのシステムとは違った形にするよう意識した。具体的には、原則的にはライブチャージは取らない、1000円持っておつりがくる店(初めはビール600円、お通し300円だった)という画期的なことだった。さらに、「ロフトプラスワンに出演する資格は誰にでもある」「有名・無名は一切関係なし。ただ条件は訴えたいものを持っていること」「他者とのコミュニケーションに積極的なこと」この三つを守ってくれればいい。トークは時間無制限、犯罪以外(?)のパーフォマンスは全て自由。おかげで今ではほとんど姿を消してしまったが、激論になればそのトークが朝まで続くこともしばしばあった。ステージではいまや伝説となりつつある乱闘、乱交(?)などもあった。

|
唐沢俊一さんも、この頃はまだ知る人ぞ知る存在だった |
烏山ロフト(1971年開店)以来、30年以上にわたって日本の音楽文化の片隅を支えてきたロフトは、当時の文化状況やロックシーン、ライブハウスのあり方への疑問からこの店を始めた。「何千円も払って、あるいは大スポンサーがついた有名人の講演会を聞きにゆく」のではなくて、居酒屋値段で酒を飲みながら話が聞けて、一日店長とゲストのトークが一段落した後、必ず客席にはマイクが回り、誰でも討論に参加できることが最大のウリだったのだ。だから酔っぱらった客もたくさんいて、さまざまな激論の場となったことは確かだ。しかしやはり、結果的に言えばこれらの理想を完全に叶えることは出来なかったのだが……(それには色々な理由があると思うが、この連載で追々明らかにできればと考えている)。
<ロフトが提出した新プラン……悪戦苦闘の日々、そして方針変更>>
ロフトプラスワンの最初にぶちあげたテーマは、「ふらりと入った居酒屋で、自分の知らない世界と出会うこと」、すなわちビールを一杯飲みに来て、突然、何か不思議な世界に出会ってしまう空間作りだった。
相変わらずだが、開店当初には多くのロフト関係の友人達が、好奇心を含め駆けつけてくれた。しかしそんなものは「御祝儀」で、店の場所の悪さもあったが、1カ月も経つと、ほとんど誰も知り合いは来なくなった。いや、店の開店なんてそういうものだとは、何度も経験してはいたが、本当に誰も来なくなったのだ。

|
ネットが今ほど普及していない時代、店に集まるフライヤーは貴重な情報源だったと言っていいだろう |
この時期、私は驚異的な売り上げ「一日600円」という偉大な日を経験した(とてもイベントの名前は書けないな(笑))。これは何軒ものお店を経営してきた30数年間で、初めての経験だった。それまでのロフトの売り上げ最低記録は、72年にロフト1号店「烏山ロフト」での2500円だったのだが、それを大幅に更新した。多分この記録は当分破られそうもないと思った。もう笑っちゃうしかないのだが、ライブの客はゼロだった(こういうときは事務所にいるスタッフを動員し、店員を客席に座らせ何とか格好だけはつける)。ライブ時間が終わって、私の友人がふらりと来て一本ビールを飲んだだけだった。「チキショー、どうせなら一人も来なきゃいいのに、その方がせいせいする……」と、しきりに私は残念に思った。こういうのを「火事場のうんこ=やけくそ」という(笑)。
私が目指した「地味な企画=出演者が有名人でもなく、街に棲息するいぶし銀の様なこだわりを持った人々の話(たとえば盆栽の話とか?)を聞いてみたい」といった企画は、全くお客さんは入らなかった。あまりにもお客が入らないので、私たちスタッフは出演者からアドレス帳を借り受け、出演者の友達にDMを発送して何とか10〜20人近くの人が集まってイベントを開催できたこともあった。出演者から「なんだ、ここにいるのは俺の以前の友達とか知った顔ばかりだな」とも言われた。悪戦苦闘の日々が続いた。多分この時点で、私が経営する会社(ロフト)全体が赤字であったら、見切りをつけて閉店していたに違いなかっただろうと思う。

|
鈴木邦男さんと。それにしても二人とも若い! |
しかし私はまだあきらめなかった。私は、ライブイベントの方針を変えた。その頃、スキャンダリズムで有名だった反権力雑誌、『噂の真相』の方針をまねることにした。また、この雑誌にも有料広告を出すことにした。そしてこの方針は、導火線に火がついたように燃え広がった。
<初期プラスワンを救ってくれた5つの柱>
「ロフトプラスワン」がサブカル界から注目されだしたのは、オープンから3カ月ぐらい経ってからであろうか? 上記に挙げたような困難な状況の中、この奇妙な空間にとても興味を持ってくれた5つの群れがあった。そしてロフトプラスワンは、この群れを柱にすることによって、少しずつではあったがマスコミから注目され、これも少しずつだが「プラスワンに出演したい」という人たちも出てきて、お客さんも入り始めた。

|
会場からも容赦ない質問や批判が飛び交った |
しかしだからといって、それで30日間いつもどんなイベントでもお客が入ってくれるわけでもなく、毎月赤字ではあったのだが、この頃を基点としてこの店は各界からそれなりに注目され始めたのだ。
その5つの柱とは次の通りだ。
1−<オタクもの> 唐沢俊一・岡田斗司夫・眠田直の「オタクアミーゴス」や「と学会」の人たち。彼らの得意ジャンルはコミックだけでなくとても幅が広く、特に唐沢さんはこの店をとても面白がってくれて、ゲストとして色々な人を連れて来てくれた。
2−<社会問題もの> ライターの藤井良樹を中心とする、中森明夫・宮台慎司など「ライターズ・デン」の人たち。彼らはもうこの時代に、マスコミのあり方に疑問符を投げかけていた貴重な存在だった。宮台慎司氏の『終わりなき日常を生きろ』はベストセラーになり、より注目が高まった。
3−<エロもの> カンパニー松尾、バクシーシ山下、平野勝之など、AV界の異端児監督たち。アダルトビデオの第2期ヌーベルバーグはここから始まったといってもよいくらい、彼らの人前でのパーフォマンスは過激で新鮮だった。他にも、すでに伝説と呼んでもいい存在だった、代々木忠、村西とおる、安達かおるの登場は大変な価値があった。
4−<政治・社会問題もの> 鈴木邦男、三上治、二木啓孝、岡留安則。彼らはやはりアウトローで、ロフトプラスワンにはとても重要な存在になった。発言を封じられた人、前科者、発言したくてもその機会のあまりない人を、彼らは引っ張って来てくれた。

|
サエキけんぞうさんと近田春夫さん。「サエキけんぞうのコアトーク」は、プラスワンでも最長シリーズなのでは |
5−<音楽もの> サエキけんぞう、萩原健太。始めの頃、新宿LOFTに出演してくれているミュージシャンでも、トークとなるといくら出演交渉してもなかなかOKはくれなかったのだが、彼らのイベントを通じて音楽も含めて喋ることの面白さ、その場でのリアクション、異論・反論を楽しむようになってきてくれ、トークライブ出演へのハードルも低くなっていったのだと思う。
<表現の自由を奪われた人々は沢山いた。そして彼らは飛躍した>
この5つの柱で共通しているのは、ほとんどがいつも舞台裏にいて、長年主役を支えて来た人々ということである。あの頃、まだまだ差別語の象徴であったきらいのある「オタク」の人たちは、自分たちがこつこつ収集した面白ビデオやCD、フィギュア等を発表できる場を探していたし、当時話題の「エヴァンゲリオン」をテーマに朝まで論争したこともあった(論争のテーマはエヴァンゲリオンの終わり方だった……私にはどうでも良かったけど)
日本ジャーナリスト専門学校の講師だったライターの藤井良樹氏は、「これがAV現場だ!」とばかりにジャーナリスト専門学校の授業にバクシーシ山下監督とAV女優を呼んで、教室内で公開フェラチオをやった。結果、情けないことに生徒の父兄から学校への抗議があって、藤井氏はジャーナリスト専門学校をクビになり、彼らは「ライターズ・デン」という、ジャーナリストになりたい人のため自主学校を作って、その会場にと企画を持ち込んできた。最高潮は酒鬼薔薇事件の臨時授業だった。
そして圧巻はやはりAVものだった。今でこそ平気でネット上にエロ映像は流れているが、当時はまだネットはほとんど普及しておらず、若手AV監督が表現する表現としても過激なエロビデオは、まだまだマイナーだった。ましてや監督やプロデューサーが人前に出て、自らの作品を流したり、AV女優を連れてきて、縛ったり、おしっこを飲ませたり、さらにいわゆる鬼畜系の人々やSMも入り込んで来てもう大変だったが、それはとても話題になった。

|
かの『噂の真相』元編集長の岡留安則氏。『噂真』休刊後、沖縄に移住してのんびりするはずが、東京と行ったり来たりの多忙の日々らしい |
政治もので一番感謝した人は、やはり新右翼・一水会の鈴木邦男さん。彼の主戦場がプラスワンになったことだった。当時『週刊SPA!』に連載を持っていた鈴木さんは、無茶無茶本を読む人だった。好奇心の旺盛な人で、右翼という立場にこだわらず柔軟な好奇心の持ち主で、政治、文学、芝居、映画とあらゆるジャンルの人たちを連れてきて話したがった。一方で、三上治(元叛旗派議長)さんは、新左翼、元ブント系の文化人をたくさん引っ張り込んできてくれた。
サエキけんぞうさんは、「ロックってもう40年近くの歴史があるんです。もうただロック音楽を聴いてれば満足という時代ではなくって、その資料から含めてロックを語る時代にも入ったんだと思います。だから僕らはただ音楽誌に提灯記事を書くだけでなく、そこに集まった人たちと議論も含めて、今のロックをみんなと喋りたいんですよ」と、プラスワンの扉をたたいてくれた。
こうして、マスコミ関係の読者の多かった『噂の真相』への広告効果もあって、ロフトプラスワンはときどきテレビにも登場するようになり、新聞雑誌の取材も次第に多くなっていった。(次号へ続く)

『ROCK IS LOFT 1976-2006』
(編集:LOFT BOOKS / 発行:ぴあ / 1810円+税)全国書店およびロフトグループ各店舗にて絶賛発売中!!
新宿LOFT 30th Anniversary
http://www.loft-prj.co.jp/LOFT/30th/index.html
ロフト席亭 平野 悠
|
