<還暦を過ぎてからのロックへの生還>
今私は、60歳を過ぎて何十年ぶりかで商売抜きで日本の音楽(ロック&フォーク)に熱中している。ハマッているといってもいい。一昨年の初めから、フジロック、ライジングサンで観たサンボマスターを筆頭に、銀杏BOYZ、曽我部恵一、フラワーカンパニーズなんかに衝撃を受け、憑かれるように「今、日本のロックって面白いじゃん」と盛り上がり「新人ロック評論家」を名乗り始めた。まさに還暦を過ぎてからのロックへの生還である。
 |
▲春の訪れがやって来そうなベランダの日だまりに、我が愛猫が逃走した。わたしゃ、あわてて靴を履き猫を追いかけた。そうしたらなんと、左右違った靴を履いていた。気がついたのは会社に着いてから。もう、「何をかいわんな、もし〜」だ(笑) |
私の会社、ロフトでは複数のライブハウスを経営しているので、いつでもエラそうに、それがたとえソールドアウトのライブでも無理矢理入場できる。ライブ中に平気で許可も取らず写真も撮る(笑・ロフト系列だけだが)。そして当たり前かも知れないが、幸運なことに私の周辺にはロックに詳しい連中がたくさんいる。新人評論家としては感謝したいくらい実に良い環境である。私はいつもそんな連中に、直球で自分が素朴に感じたことを投げ、私の勘が当たっていたり、全くの的はずれだったりするのを楽しんでいる。さらには自社刊行物のフリーペーパー『Rooftop』の名前を使って気になる表現者にインタビューを申し込んだり、いろいろ音楽関係者に無理難題を持ち込んだりしているが、これもまた年の功か(?)、「平野さんじゃしょうがないな」っていう感じでいろいろ思っていることが実現したりする。だから私も、ロックに関して当然勉強もする。もう年だし血圧も高い、そして生存という残された時間もあまりない。さらにはいつ飽きが来るか心配だが、新しいバンドも古いバンドも精力的に聞いている。
1970年代、すなわちはっぴぃえんどから始まる日本語ロックと、中津川フォークジャンボリーが象徴するフォーク、ニューミュージック系。私は日本で最も、それらのライブシーンの現場に立ち会ってきた一人だろうと自負している。それはひとえに、ライブハウスなんていう言葉さえなかった70年代初頭から、この奇妙な空間を、表現者、お客さんそして店側スタッフとともに維持し育ててきたからなのだろう。
そんな古参ジジイが、90年代にはもはや霧消してしまった(と少なくとも私は思っていた)「日本語ロック」にはまっているなんてシャレにもならないが、世界や社会の激動に背を向け、日常におけるささやかな幸せだけを唄うのが現在のロックのあり方とする「主流」には、私は相変わらず断固「否」としたい。これもあの政治の季節を生き抜いてきた偏屈オヤジの習性なのである。そして今、私自身はまさしく輪廻のように、20年ぶりにロックな世界に舞い戻ってきたつもりなのである。がんばろ〜ぉ、突き上げる空に〜っと……えいえい〜おっっ!(笑)
<お笑いとロックの融合、ダイノジ・ロック・フェス>
 |
▲ダイノジ・ロック・フェスが行われた川崎クラブチッタ。移転していたんだ。昔のチッタは埋め立て地にあったため、1000人規模の若者が跳びはね出すと、100m先の麻雀屋のパイが倒れたそうだ |
2月2日、川崎のクラブチッタの「ダイノジ・ロック・フェスティバル」に行った。コンセプトは「お笑いとロックの融合化に挑戦?」と見た。これは実に面白いテーマを持ったイベントだった。ロフトは今、ほんの20数坪の小さな表現空間、ネイキッド・ロフトで、「音楽とトークの融合」をめざしているが、川崎までノコノコ電車を乗り継いでイベントに参加したのは、お笑いを含めて私が今、この瞬間、観たい出演者ばかりのラインナップだったからだ。まさに今、「このイベントに行かにゃ〜オシメェよ」っていう感じの出演者群だった。
私が到着したのは18時過ぎで、丁度ニューロティカのライブが終わる頃だった。DMBQを初めて観た。すげえ〜! 昔のノイズバンドの王者・非常階段を観ているようだった。予定調和を見事に廃して、いつ、何が起こる解らないといった、ロックが持っている本来の危うさがあってゾクゾクした。チッタは音がいい。素晴らしくいい。
いわゆる爆音バンドが中心のラインナップの中で異色なトライセラトップスのステージは、複雑な気持ちで観た。ボーカルの和田唱は迷っている感じに思った。このバンドのライブを観るのは2度目だが、ドラゴンアッシュと音楽シーンを二分していたあの頃のきらめきはもうないと思った。それは特に、次に出てきたサンボマスターと比較すると、見事に存在感(リアリティ)の違いが出ていると思った。サンボは観るたびにその立ち位置が正解かどうかわからないがものすごい存在感が出てきて、圧倒されてしまう。
お笑いのメンツもなかなか良かった。猫ちゃん(猫ひろし)のステージを久しぶりに観た。彼はプラスワンのイベント「ゴングショー」から出てきたスターという意識が私にはある。ブレイクした当初、多くの連中は「猫ひろしの寿命は短い」と言っていたけれど、猫ちゃんはマンネリを超えた素晴らしい存在になった。マキタスポーツの矢沢の物まねは相変わらず抜群。何度も観てるのにまた笑わせてもらった。
次々とめくるめくステージが繰り広げられ、時間を忘れてしまうくらいだった。ライブ中、私は留まるべきか帰るべきかを悩んでいた。場所は川崎、いくら椅子がある2階関係者席とはいえ、この年でしかも高血圧でこの爆音の中もうめまいがしてきていた。次々に聞き漏らしたくないバンドが出てくる。今の私にとっては「オールナイトライブ」はさすがにしんどい。私はなるべくタクシーには乗らないようにしているし、都内ではないので深夜タクシーで東京に帰るにはちょっと高すぎる。何とか銀杏BOYZまでは観れるかと思ったがかなわず、川崎駅から0時10分発品川行きに飛び乗った。山手線池袋行き、京王井の頭線永福町行きで明大前で乗り換え、京王線桜上水行きと、なんと4回乗り継いだ全部が最終電車だった。こんなことは初体験だった。さすがに疲れた。手前味噌になってしまうが、やはり新宿ロフトは年寄りには最高にいいと思った。新宿ロフトはラウンジという逃げ場がある。疲れたらラウンジで一杯飲み直してから、「よ〜し!」と気合いを入れてまた音の洪水の中に入れる。
<ダテに年を食っている表現者はいない>
ビートルズが来日して40年が経った。老いも若きも誰しもが、音楽を聞いて鳥肌が立つような経験をしたことがあると思う。ロックやフォークが若者だけの音楽ではないのは明らかだ。
川崎では若い連中の勢いに圧倒されたが、今年になって、「熟年表現者」の醸し出す音楽が実に良い。エンケンもリザートのモモヨも素晴らしかった。大塚まさじや友部正人も、どこまでゆくのかというくらい、どんどん良くなって行っている。3月28日には、新宿ロフトで「LOFTの春二番2007」と題するライブが行われる。出演はThe Voice&Rhythm(石田長生/正木五郎/藤井裕)、有山じゅんじ、金子マリ、北京一、山田タマル。そしてサブステージで大塚まさじの弾き語りがある。機会があればぜひ、ライブ会場に聞きに来て欲しい。一時代を作った古き奴らは、そうは簡単に終わってはいないのだ。
<平野悠トークライブ出演情報!!>
「21世紀のロックンロールとは何か? VOl.2」
【日時】3/24(土) OPEN17:00/START18:00
【場所】Naked Loft(tel.03-3205-1556)
【出演】KEITH(ex-ARB/Groovin)/平野悠(ロフト席亭)/吉留大貴(フリーライター)/今田壮(LOFT BOOKS)
【料金】前売\1,500(+1drinkから)/当日\2,000(+1drinkから)
※前売りチケットはNaked Loftにて電話予約受付中!
今月の米子♥
今月の米子とおー君。ご存じ我が家のケットーショー付きスコティッシュとアメショーのツーショット
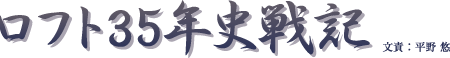
ロフト35年史戦記 第24回 90年代ロックへの違和感(1991〜1992年)
<約10年ぶりに見た日本のロックシーンとは……>
日本の音楽(ロック)文化をその底辺で支えてきたライブハウスは、時代と共に変わる。91年、私が10年ぶりに日本のライブハウスで目にしたものは、それはとても違和感を覚える奇妙な風景だった。
時代は、高度成長期が絶頂を迎えたあの愚かなバブルを経て、ソ連邦が崩壊し東西冷戦体制が終わった年だ。音楽的にはイカ天・ホコ天のバンドブームの直後だった。何が何でも日本のロックの最前線に戻りたかった私は、当時の新宿ロフト店長・小林茂明(現ロフトプロジェクト社長)に勢い込んで尋ねたのだった。
平野「今、ロフトのシーンとは何か? どんなバンドを見たら現在的ロフトとか日本のロックの最先端のシーンが理解できるんだ?」
小林「今のシーン、ちょっと複雑で悠さんにはよく解らないと思うけど、とりあえずカステラ、ピーズ、クスクス、ウルフルズ、ニューロティカ、スピッツなんかを観て下さい」
平野「確かに今や浦島太郎状態だものな。カステラ? スピッツ? ピーズ? なんだそれ? カステラはお菓子の名前だろ? ピーズはネックレスか? スピッツって神経質で誰にでも吠える犬だな(笑)。昔はバンド名からほとんどその傾向はイメージ出来たものだが、これじゃ〜全く無理だな?」
小林「バンド名で善し悪しを決めてしまうのが平野さんの昔からの悪い癖です。あの辻仁成のエコーズもそうだし、デモテープも聴かないで名前だけで出演やイメージを決めるような時代じゃないんです。昔と違って東京にはライブハウスもたくさん出来ましたし。競争相手もたくさんあります」
平野「昔からの言葉で名は体を表すっていいうけど……そうか解った、気をつけよう(笑)」
<軽薄なメッセージがあふれるシーンへの違和感>
私が新宿ロフトに現場復帰して最初に観たのは、期日はいつだったか忘れたが、確かカステラとかピーズとかの若きバンド群だった。そしてそれらのバンドを次々観戦していった。
その当時の私は、「誤解を恐れず」に言わせて貰えば、彼らが醸し出すそのメッセージの意味のなさとノリの軽さに、衝撃のあまり思わず考え込んでしまった。「日本のロックはここまで変質してしまったのか?」といった感覚を持った。それは驚きというよりも、多分落胆したと言った方がよいのだろう。
そこには私が期待するというか、イメージしていた「思想(=カウンターカルチャー)としてのロックの立ち位置」はほとんどなく、聴衆は健全そうな若い少年少女ばかりだったし、カステラやビーズは「ピーマンなんか食いたくねーよ」「ビデオ買ってよ」と、なんの意味もなく(?)リズミカルに唄い、クスクスの「寂しくないんだ、みんなで手をつなげば……」なんていう歌詞が私の耳に入って来ると、私はもう訳がわからなくなってきていた。ライブハウスの店内は、少年少女の爽やか健全ムードが満ちあふれ──確かに軽いウエストコーストっぽい、ノリのいいリズム隊は素敵だったが……──まるでジャニーズのコンサートのようにみんな両手をゆらし、一緒になって歌を歌ってウェーブしている光景には、「こりゃ〜まるで仲良しクラブ的歌声喫茶ではないか」と思ったくらいだ。45歳になっていた私は、世界中を回ってきていろいろな音楽を聴いてきたつもりだった。とにかく彼らのお子様ランチ風な歌詞にはとまどうばかりだった。
そんなことをつい最近だが、音楽ライターの吉留大貴氏に質問してみた。すると、「平野さんが帰ってきた90年代は、ラフィン(・ノーズ)やブルーハーツの重いメッセージからのクールダウンの時代だったんです。意味性からの解脱なんですよ。彼らは出来るだけ意味のないことを唄い、歌詞がないと唄えないというだけでしか歌詞をとらえていなかった。だから平野さんのとまどいは当然なわけですよ」と彼は言うのだった。
新宿ロフトには、あの入場し階段を下りるだけでも不良の臭いがする、薄汚くっていつも何か起こりそうな危険で妖しげな雰囲気はもうなかった。突っ張っている演奏者もお客もいなかった。私は、「おい、不良だったあいつら、俺がこよなく愛した毒と社会を斜めに見る反抗的スピリットロックはどこにいったのだ」と、思わず嘆き悲しんでしまった。10年の空白の歳月が生んだ、なんともいえないくらいの断絶が私の目の前には存在していると感じた。
「そうか? 今のロックに文化や社会との接点である思想を求めてはいけないのだ。この世紀末の時代では、ロックミュージックが意味性を歌い上げてはいけないのだ」と痛切に思い、またもや私の居場所が今の日本のロックシーンにはない事を痛感し、日本に戻って「もう一度ロックの最前線にいたい」という自信と意欲がどんどん失せて行くのを止めようもなかった。
<ライブハウスのジャンルごと棲み分けの弊害>
一方、見方を変えると、東京の音楽シーンではバンドブームを経て、ロックのジャンル別による演奏空間の棲み分けが出来上がっていた。例えばビジュアル系は「目黒鹿鳴館」、フュージョン系は「六本木ピットイン」、ブルース系は「高円寺JIROKICHI」、フォーク系は「吉祥寺曼陀羅」というように、ライブハウスごとにジャンル分けがはっきり出来上がっていたのにはビックリした。
私の長年の理論で言えば、ライブハウスとは街の中に息づいているものであり、「素敵な音楽は可能な限りどんな系統でも取り込みたい」というのが、ライブハウスを作った原点だった。それはまさしく「ジャンルレス」だった。新宿ロフトのブッキングを見ても、70年代私がこよなく愛したメッセージフォークなど跡形もなくなっていた。大塚まさじや森田童子、長谷川きよしのサンデーサンバセッションの次の日、フリクションやブルーハーツが演奏する。その音楽の持つ雑食性というか、色々なジャンルにふれあい影響しあい、勝負を楽しむスタイルはもうなくなっていた。
当時、「ライブハウス・ロフトのポリシーは何か?」とブッキング担当者に聞くと、「パンク・ニューウェイブ系」だという。「何でそういう風に決めつけてしまうのだ。君はブルースとかフォークとかいろんなものを聴きたいと思わないのか? 俺がロフトの最前線にいた頃には、あらゆる音楽に好奇心があったよ。だから長いことライブハウスを続けることが出来た。それを多くの人に伝えるのを使命としていた気もする」という私の意見に対し、「ブルースやフォークですか? 今の時代、ロフトがフォークをやっても、お客は入りません」という答えには愕然としてしまった。これはミュージシャンやレコード会社、そしてプロダクションとライブハウス同士の分断であり、新しい音楽の登場を疎外するものでしかないと私は漠然と思ったのだった。
 |
▲ロフトの歴史はライブハウスの歴史でもあり、(おじさんの趣味の)闘争の歴史でもある!? |
<大資本のデカバコと街のライブハウスの違い>
西新宿の薄暗い地下に下りていっても、私が過去に知っていたマネージャーや音楽関係者と現場で出会うことはほとんどなくなっていた。私は若い連中の中でぽつんと、群衆の中の一人を意識していた。まさしく日本のロックに疎外された私は居場所を失ってしまっていた。悲しいかな、もう一度、昔のように日本のロックの最前線にカムバックしたいといった幻想は、見事に吹き飛んでしまったのだった。
当時私の目に見えていたのは、こんな状況だった。ロフトと一緒に東京のライブシーンを築き上げてきた、渋谷屋根裏、新宿ルイード、代々木チョコレートシティはなくなっており、新宿ではあの大企業・日清製粉のパワーステーション、渋谷では西武資本のクラブクアトロが日本のライブハウスの代名詞的存在としてその名を謳歌していた(これらのデカバコをライブハウスといってよいのかどうかは疑問だが)。特に同じ新宿にあって、東京のライブシーンはこのパワステを中心に展開されているということになぜか腹が立った。さらには新宿歌舞伎町に、1000人キャパのリキッドルームが出来るという噂があった。
私たち中小ライブハウスは、日本のロックミュージックを底辺で支えて来たという自負があった。人気が出て集客を見込めるバンドに、対バンとして新人バンドを前座に組み込み、「このバンドも聞いてくれ」というメッセージを長いこと送り続けてきた。だから赤字覚悟で新人バンドにその場を開放した。多くのリスナーは、そうやって見知らぬ新しいバンドと出会った。ライブハウスで支持するバンドを観て、そこで知り合うことによりファンクラブが結成されていたりしたのだ。しかし1000人以上収容規模のハコはそんなことには関係なく、中小ライブハウスから輩出した人気バンドをさらってゆくだけのドロボー野郎にしか見えなかった。
確かに時代と共に新たなスポットが生まれてゆく中で、それまで文化を担ってきた古い店がなくなってしまうのは仕方がないのかもしれない。だが私にとってライブハウスとは、確かにこの大手資本の論理と同様に「経済活動」の場ではあるが、一方で「文化発信の震源地」としても機能させたいという意識もあるわけだ。空間としては、これから世に出てくる新人バンドの活動の場所でもあるわけだ。デカバコで「新人デー」なんてやっているのを見たことがなかった。
<パワステ、クアトロに勝つしかない>
そんな中、ロフトはどこか元気がないように見えた。私には大資本のデカバコばっかりが輝いて見えた。当然かも知れないが、相変わらずインディーズで人気が出るとすぐにメジャー契約したがるバンド群。ロフトワンマンに成功すると、次はパワステとかのデカバコへ。小さな動員力のあるバンドのパイを取り合う中小ライブハウス。対バンの数も増えていったが、その論理は「1+1=2」でしかなく、更には各バンドに対しての「ノルマ制」に帰結していった。
いくらメジャーバンドになった連中が「俺たちはロフト出身だ」と武道館や東京ドームのステージで言っても、私はちっともうれしくなかった。「そう言うならせめて1年に2〜3回は生まれ故郷でやれよ。ビートルズだってグレイトフルデッドだって、でかくなってもそうしていたよ」とぼやくしかなかった。まあ、バンド連中ががいくらそう思っていても、レコード会社やプロダクションは承知しないだろう。そう、「ビジネス」として考えれば、キャパ200〜300のライブハウスで演奏するメリットなんて、ほとんどないのは当然なのだから。
そうこう考えているうちに、私はやっと、自分を奮い立たせる目標が見えてきた。「ロフトはロフトなりのやり方で、デカバコであるパワステ、クアトロに勝つしかない」と……。その為にはまず、目の前の立ち退き問題をやっつけるしかない。
私はビル建て替えの為、新宿ロフトに「立ち退き」迫っているオーナーと精力的に交渉した。「我々は都市再開発を全く拒否するものではない。さらには居座ってゴネ得をするつもりもない。ただ私たちの要求は一つ、ビルの建て替えに協力するから、その地下を我々の自由に設計させてください。家賃も補償金も市価に準じても良い」という要求をした。銀行回りから始め、私は自分の持っている全てをそこに投入し勝負する気になっていた。私には、この東京のライブシーンの先頭を走り続け、作り上げてきたのはロフトだという愚かな(?)プライドがあった。今ならまだパワステに勝つチャンスはある。確かにもう何十年もやっている現在のロフトでは、キャパや機材も環境も限界である。これでは勝てないという焦りそのものが私の心を支配していた。
私は、新宿ロフトが入っているビルのオーナーを、パワステやクアトロにも案内した。「大手企業の日清製粉や西武ですら、自社経営のライブハウスを作る時代なのです。もうあのハードコア、パンクの時代の暴力沙汰や付近住民からの立ち退き沙汰には絶対しないので許可願いたい」と少々の嘘も含め懇願した。我々は設計図を書いた。ビルオーナーがイメージしたファッションビルに若者文化の象徴である「ライブハウス」を作り、文化発信の場を作ることがこれから出来るビルにとってどれだけメリットがあるかを説明した。交渉は順調に行った。(次号に続く)
 『ROCK IS LOFT 1976-2006』
『ROCK IS LOFT 1976-2006』
(編集:LOFT BOOKS / 発行:ぴあ / 1810円+税)全国書店およびロフトグループ各店舗にて絶賛発売中!!
新宿LOFT 30th Anniversary
http://www.loft-prj.co.jp/LOFT/30th/index.html
ロフト席亭 平野 悠
|
