かくして完璧すぎるライブは終わったが……。
数多いヒットソング、それを支える難波弘之(key)等の豪華メンバーによる完璧なアンサンブル、アカペラがあり、マイクも通さない生唄までもやり尽くして、春の中野サンプラザライブの興奮は最高潮に達していた。シュガーベイブ「DOWN TOWN」を含む数度のアンコールで、終演予定の21時はとうに過ぎていた。アンコール最後の「YOUR EYES」を終えて、圧倒的な聴衆の拍手と歓声に囲まれながら何かやり残したことがあるような、目を細め名残惜しそうにステージから引き下がって行く山下達郎氏(56歳)に、「達郎さん、もう一発弾けちゃいなよ」と問いかけている一聴衆の私がいた。
彼にとって6年ぶりのツアー、そして私にとっては30年ぶりに観るライブでの山下達郎……ブルーのニットの帽子、紺碧のシャツ、そして品のいい高そうなGパン、トレードマークである、30数年前には「反体制の象徴」とされた細いロングヘアー、そのヘアーがピンスポットに浮かび上がって緑色にキラキラ光っていた。久々に観る達郎さんは、過去に観たことがないほど健やかにステージに立っている。還暦に近くなった多くの初老の音楽家のように、ブクブク太り伸びない高域を無理矢理出そうとしている無様さとは違って、洗練されたスマートな容姿で驚異的な声量を誇りながら歌っていた。凄い……その存在感、完全にやられた……。私の全身は、達郎さんの心地よい緻密に組み立てられたリズムと高域のボーカルを生かしたサウンドの世界にどっぷり入り込んでいった。彼のポップミュージックへの一途な愛とひたむきな努力は、私にだって伝わる。3時間を超えるのに「心地よく完璧」にライブはあっという間に終わった。

 |
1975年9月号ルーフトップ(35年も前の事だ)はまさに我らが若きホープ、山下達郎特集だ。右下にはナイアガラレーベルの広告が入っている。この頃のルーフトップはとても質が高く、まさにロック界のオピニオンリーダー誌だった。その時代、街のいちライブハウスがこんなフリーペーパーを毎月発行するなんて凄いでしょ。
|
<ちょっと待てよ……今日のライブは……銭湯で考えたこと……>
ライブの感動と、今回チケットを頂いたお礼を達郎さんに伝えたくて、終了後に私は楽屋を訪ねたが、あまりもの業界関係者の多さに閉口してそっと立ち去り、いつも深夜に行く下高井戸の銭湯に急いだ。
「うん、個人的に今夜のライブは今まで観てきた達郎さんのライブの中でも5本の指に数えられるだろうくらい良かった」と、今回私をライブに誘い同行した音楽ライターの吉留大貴氏の言葉が浮かんだ。だが同時に、「……ちょっと待て。私はあの達郎さんの心地よさをただ体感しにライブに行ったのか?」と、誰もいないがらんとした湯船に浸かりながら、一人ぽつんと今夜のライブでのことを思い返していた。
「はたして私は35年前、シュガーベイブ時代の荻窪ロフトで出会った時のように、今夜、身の毛が逆立つくらいの戦慄を覚えたのか?」といったところで、私は思考停止状態に追い込まれた。
今まで一度も語ったことはなかったが正直に言おう。私にとっての山下達郎は「サザンやアルフィーやその他のポップミュージックの、数々の成功した音楽家とは違った存在なのだ」。
確かにこの夜のポップミュージックを知り尽くした山下ワールドは完璧だったが、しかしそれはポップミュージックとしての完成度であり、現実のリアルな世界に立っている私達や今の若い世代の心までも激しく揺さぶるライブだったのかというところで、私は迷宮に入り込んだのだ。
今でも、シュガーベイブ時代の山下達郎を私ははっきり覚えている。達郎さんは還暦を過ぎた私より8歳下で56歳。いわゆる学園闘争が日本全国で巻き起こり、ベトナム反戦行動が吹き荒れる70年代の「政治の季節」にその青春を過ごした。多くの若者が「古い価値観」を乗り越えようと街頭に飛び出した時代だ。この時代、世界中に新しい文化が、音楽、映画、演劇、文学にと巻き起こった。
1973年、四谷の小さな喫茶店で「新人バンド・シュガーベイブ」(大貫妙子も在籍)が生まれた。当時ロフトのブッキングマネージャーで、今やアメリカンロック屈指のレコードコレクターと知られる長門芳郎(伝説のレコードショップ・パイドパイパーハウス店長)氏が開店したばかりの荻窪ロフトに、「まだ無名だけど凄いバンドがいるんだ」と連れてきてくれた。
その後、1975年4月に大瀧詠一氏の主催するナイアガラレーベルからシングル「DOWN TOWN」、アルバム『SONGS』でレコードデビュー。しかしわずか1年足らず後の1976年3月31日、4月1日、荻窪ロフトで解散ライブが行われ、その短いバンドの歴史に幕を閉じた。76年といえば新宿にロフトができた年だ。巷では、「一部不良の音楽」と言われたロックがやっと市民権を少しづつ獲得し始めた時代だった。深夜放送を中心に日本のロックは若者達に支持を獲得していった。このバンドの解散理由は「経済的問題」が一番大きかったそうだ。こういった才能あるバンドの連中のほとんどが、飯が食えなかった時代だったのだ。
<あの頃私達は達郎さんに何を期待し何を支持していたんだろうか?>
「今、音楽家の中で一番過激でアナーキーなのは山下達郎だ」という話はいたるところで聞く。「俺はとうの昔に日本の政治には絶望している。だから政治的発言はしない。チャリティにも出ない」と本人が言ったことも伝え聞いた。しかし戦争と平和の問題、悪化する地球環境問題や貧困や差別に関して、彼のパブリックイメージとは異なる達郎さんの種々の発言が、どこからとなくオフレコで漏れて来る。この夜のMCで達郎さんは、「残りの人生で音楽活動をあとどれくらいできるかを真剣に考えるようになった。そんな中で声が出ているうちにライブをやっておきたいと思い、さらには30年近く使い慣れてきた大阪フェスティバルホールが取り壊される、そしてこの中野サンプラザも数年のうちになくなる、と聞いて、今回6年ぶりのツアーをする気になった。今、凄い時代になっています。音楽で革命は起こせないけれど、歌にできることは、戦争は止めることはできないかも知れないけれど、傷ついた心や悲しみを癒したりはできるのだと思っています」と衒いながら言った。
「音楽で革命は起こせない」勿論正論ではある。30数年前の俺たちにとって、達郎さんの音楽こそが「革命」そのものだった。あの激動の70年代に、あんたは何かを変えたくって音楽を選んだのではなかったのか? そして今でも達郎さんは心の中では本当に誰よりも音楽こそが人間を豊かにし、平和にできると信じているんじゃないのか? 達郎さん……俺たちはいまだにあの頃のように「革命前夜」のままにいるんじゃないか……。
小さな街の小さな銭湯の最後の客になって、暖簾を頭で押して深夜の路地に出た。今夜のライブの興奮と疑問符を持ったまま、私は新緑の街路をただ愚直に歩いた。
今月の米子
何を思うか(狙って)米子の眼・いい女になってのでしょう。アメショー3歳。素晴しい、あんたの佇まいはいつも孤高で気ぐらいは高い。
お詫び…前回までの連載の最終回予定「大海原を行く」は都合により先送りになりました。すみませぬ。
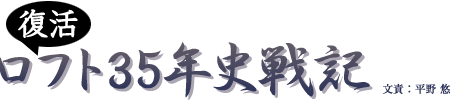
ロフト35年史戦記・後編
第41回
怒濤の新宿LOFT20周年記念イベント-1(1996年)
伝説の新宿LOFT20周年記念事業に関して、私はほとんど参加していない。だからそのことを自分の問題として書きようがない。だが、ロックが誕生してから半世紀という歳月を経て、過去が現在に繋がっていて、その中に私たちロフトのロックの歴史がある。小さな、世紀末な新宿の薄汚い地下の薄暗い場所に、まるで蛸壺のようにへばりついていたロックな空間が新宿LOFT(1976年オープン・65坪・キャパ300)だったのだ。
当時としては日本最大の本格的ライブハウスの出現であり、烏山、西荻窪、荻窪、下北沢とライブハウスを展開してきた私にとっては、ライブハウスの完成型でもあった。現在、新宿歌舞伎町に移転した新宿LOFTも、今年で通算33年にもなろうとしている。この連載である「ロフト35年史戦記・新宿LOFT編」も1994年のロフト立ち退き裁判(2007年12月号掲載)で終わっている。しかし多くの当時を知らない若者達から、是非新宿LOFTの歴史の連載を続けて欲しいという強い要望もあり、つたない記憶を頼りに、私なりに偉そ〜に勝手に再開することにした。
先日、ロフトにもなじみの深い忌野清志郎さんが亡くなった。我々70年代ロック世代の第一線で活躍してきた素晴らしい音楽家も、どんどん年を取ったりして亡くなってゆく。寂しい限りだがこれも一つの歴史である。さあ、勇気を持って先に進もう。

|
20周年アニバーサリーを準備するプロジェクトチームの机には企画書が山と積まれていた。
う〜んたいへんだ〜!
|

|
おっと、もう武道館の写真を掲載したか? かのARBの石橋凌さんは「ロフトのステージに上がる階段も、武道館の階段も我々の中では同じなんだ」と言うのが口癖だった。BOφWYの氷室京介は東京ドームで「ようこそ、ライブハウス東京ドームに…」と挨拶したそうだ。
|
<日比谷野音から武道館への挑戦>
1997年2月。寒さ震える冬。バブルが完全崩壊し巷では不景気真っ最中。神戸で連続児童殺傷事件(通称・酒鬼薔薇聖斗事件)が起きた。特に被害者の頭部が「声明文」と共に校門に置かれ、地元新聞社に「挑戦状」が送られ、犯人が普通の中学生であった点でも社会に衝撃を与えた。日本のロック状況でいえば、この年の夏、フジロックが何万人も集める野外フェスとして始動し始めた。
この前年、ロフトプロジェクトの代表取締役社長に小林茂明が就任した。元新宿LOFT店長だった小林茂明は、1994年7月10日、日比谷野外音楽堂で行われた新宿LOFT立ち退き問題に抗議するイベント「KEEP the LOFT“で で で 出てけってよ”」を仕切り、準備期間2カ月で100名近い音楽家や文化人を招請し圧倒的に成功させ、新宿LOFTの立ち退き問題を一つの社会現象にした。同年11月、プロダクション「ピンクムーン」を設立。1995年4月、新宿ロフト立ち退き訴訟に勝利的和解成立。同年、下北沢駅前にレコードショップ「TIGER HOLE」オープン(後に新宿駅西口に移転)。そして1997年には「ロフトレコード」を立ち上げるなど、精力的に行動している。まだロックに勢いがあった時代だ。
さて私は、この時代ほとんどロック関係には興味がなくなって、というより時代を読むこともできず、ロックそのものが解らなくなっていた時期で(……今でもそうだが)、会社の音楽関係は新宿LOFT生え抜きで若い小林(32歳・当時)に任せきりであった。
私は新しい遊び場「トークライブハウス・ロフトプラスワン」(1995年7月オープン・30坪・新宿富久町)という、摩訶不思議な空間を新宿の御苑近くに作り、その隠れ場的存在に熱中していた時代だ。ロフトプラスワンは行き場がなくなった私の遊び場であり、そのサブカルというテーマやトーク(しゃべり場)というカテゴリーについては、ロックバカオンリーの会社の連中が理解できるはずはなく、誰からも何も言われないことを盾に私は好き勝手にその場を孤高のごとく運営し楽しんでいた。なんと一日の売り上げが600円という、私が40年近くライブハウス空間を経営して初めての驚異的な売り上げを経験して、ぶっ飛んでいた頃だった(笑)。かつて常連出演者だった中森明夫氏から、「新宿サブカル御殿」と言われる少し前だ。
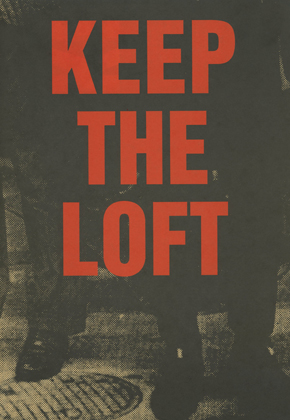
|
1994年日比谷野音で行われた「KEEP THE LOFT」のパンフレット。サカグチケンさん渾身のデザインで業界の評判を呼んだ。
|
<武道館への道 第1章>
1995年10月だったと思う。小林から私はある相談を受けた。この時期私は、新宿富久町にあったプラスワンの上階に個人的事務所を借りていて、ロックのロフトで稼いだお金をせっせと赤字続きのロフトプラスワンに消費して社会還元していた(笑)。だからロフト本社の事務所にはほとんど顔を出していなかった。小林は、私の事務所まで色々な書類を持ってやってきた。
「悠さん、久しぶりです。たまには事務所に顔を出してください。それで今日は相談があります」
「なんだ、俺は忙しい。プラスワンの赤字のことだったら今は聞きたくない」
「……で、来年(1996年)はロフト20周年の節目にあたります」
「ふ〜ん、そうか? 新宿LOFTってまだあったのか? でもそれは違う、俺がロフトを始めてから25年近く経つはずだ」
「いいえ、新宿LOFTのことです」小林の表情が私に対してのあきらめに変わってゆく。
「ふ〜んそれで……またお前は記念だって言って何かをやろうとするんだろう。基本的に俺にはそういう記念なんちゃらイベントって興味がない。話しても無駄だ。勝手にやれ」
「そうは言われても、この計画はボクが勝手に進めるわけにはいきません」
「なんだそれって、そんな大げさなことか?」
「10周年は先代の店長が新宿厚生年金でやりました。BOφWYもハートビーツもルースターズもやりました。20周年はロフトの歴史を1日で見せられるようなものにしたいんです。それには今のロフトのキャパシティでは到底収まりません。この20年、日本のロックは成熟の域に達してきたし、ライブハウスを基点としたひとつの頂上があるとするならば、それは“ロックの殿堂”として名高い日本武道館以外に考えられない。武道館のステージに立つのはバンドにとってひとつの夢ですから。それに、ロフトのようなミニマムな発信基地と相反する場所であえてイベントをやる面白さもあると思うんです。つまり、武道館を日本一大きなライブハウスにしたいんですよ。ステージをロフトと同じように市松模様にして、大御所から新進気鋭のバンドまでが同じステージに立ってもらう。これまでのロフトがバンドの世代に関係なく、ポテンシャルの高い音楽をずっと発信し続けてきたように。その意味で、僕はこのイベントがこれから日本のロックを担う新しいバンドたちへの橋渡しにもなると思うんです」
「アホか〜おめえ、武道館って、いちライブハウスごときがやれるはずないだろう。新宿LOFTだって300人詰め込めば酸欠になる。今、たかが30坪、客席50そこそこのキャパの所で四苦八苦している(笑)俺には想像ができん。武道館一日借り切っていくらかかるんだ?」と私は尋ねる。
「空箱で***万です。でも何とかスポンサーを探して赤字無しでやってみたんいんです。許可をください」
「ちゃんとしたマーケッティングをして企画書を持ってこい」
あきれてものが言えないくらい小林は真剣だった。その日私は、小林の提案にそっぽを向き通した。
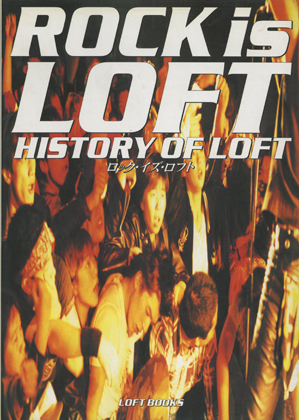
|
1996年に立ち上がった「ロフトブックス」はこの20周年記念ライブに向けて、ロフトの全スケジュールを網羅した「ROCK is LOFT」の編集作業に取りかかった。な、なんとこの本は当日武道館で6000部も売れた。国枝編集長のセンスが光る本だった。
|
<武道館への道 第2章 「GO!GO! LOFT-20th anniversary」の企画書はできた>
時はいわゆるイカ天・ホコ天の空前のバンドブームが終わり、第二次ライブハウスブームも過ぎて、大型ライブハウスとして登場した渋谷のライブインや新宿ルイードも姿を消していた。さらには、いわゆる日本の音楽シーンを揺るがせた東京ロッカーズのパンクシーンも終わっており、その時代を生き残ったバンド群の、日本のロックの真価が問われる時代になっていた。
この頃、ロフトプロジェクト社長・小林茂明は「新宿ロフト20周年・武道館への道」実現のために走り回っていた。彼にとってもロフトにとっても壮大な挑戦だった。それにロフト創設者の私は、そんなことにはほとんど興味がないと言うのだ。
小林と彼のブレーン達(ホットスタッフの桜井直己氏と鈴木太五氏、スマイリーズの原島宏和氏、ARB OFFICEの藤井隆夫氏、当時の新宿ロフト店長だったマリモ、おなじく下北沢SHELTER店長・平野実生)が、何日もかかって制作した新宿LOFT20周年記念ライブ企画書を私が見れたのは、それから半月も経たない雨の降りしきる寒い日だった。もちろん小林一人では全く実現不可能な話だったのだ。ロフト音楽部門の総力を挙げた、記念事業のスケールとしては空前のものだった。企画書を見た私にとっては、「はたしていちライブハウスがこんなことできるのか?」という内容だった。
それは、ただ武道館でライブをやり遂げるという単発的な内容ではなく、ライブスケジュールは日比谷野外音楽堂から始まって、新宿LOFT(13日間)〜渋谷公会堂(2日間)〜川崎クラブチッタ(3日間)、そして最終日の武道館で終わるという空前絶後の内容だった。
「凄いボリュームだな? こんなブッキング可能なのか?」と私は小林にやおら尋ねる。
「可能だと思います」
「う〜ん、俺には何も手伝えることはない気がする。成功の可能性はあるのか?」
「誰も始めから失敗を予定して企画するものはいません。スポンサーも探します。タイアップのテレビもマスコミも総動員してみせます」
「でも、“この1カ月間でロフトの20年の歴史を見せてやる!”ってほざいても、かつて新宿LOFTの看板だったARBもアナーキーもルースターズもBOφWYも解散したし、サザンや山下達郎さんや坂本龍一さんや、元ティン・パン・アレー系の重鎮が出演してくれるとは思えん。今のロフト出演のバンドのメンツで武道館を満員にできるはずがない。赤字覚悟のラインアップか?」
「いえ、満員にできます。スピッツ、ウルフルズ、ハイロウズや布袋寅泰さんも石橋凌さんもキースも、ルースターズの面々も、泉谷しげるさんにもいい感触を得ています。解散したバンドの面々には個人参加してもらい、普段では絶対観れないスペシャルセッションをします」
「それが可能ならば凄い話だが……。〜記念とかいって高い入場料を取るのはやめてくれ」
「これから動きます。許可をください」
その瞬間、その場の空気がぴーんと張った様に見えた。小林は固唾をのんで、私が次の言葉を発するのを待った。(以下次号へ続く)

『ROCK IS LOFT 1976-2006』
(編集:LOFT BOOKS / 発行:ぴあ / 1810円+税)全国書店およびロフトグループ各店舗にて絶賛発売中!!
新宿LOFT 30th Anniversary
http://www.loft-prj.co.jp/LOFT/30th/
ロフト席亭 平野 悠
|
